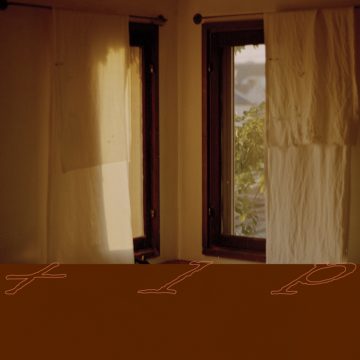LISTEN HERE
https://linkco.re/4H3nqaAN
1: Heaven
2: Pragma
3: one window (instrumental)
4: Pluralist
2025年2月14日(金)オリジナルEP『+1P EP』をリリース。アルバム『unpeople』を経て、蓮沼執太の現在地が集約された4曲を収録。
国内外での音楽公演をはじめ、映画、テレビ、演劇、ダンス、ファッション、広告など様々なメディアで縦横無尽に音楽制作を行う蓮沼執太。2月14日(金)に、オリジナルEP『+1P EP』をリリースする。『+1P EP』は、国内外から高い評価を得た前作アルバム『unpeople』(2023)以降に行ってきた立体音響によるサウンド・パフォーマンス『unpeople + 1 people』の「+ 1 people」からネーミングをとったタイトルになっている。
2月5日(水)に配信されたEPの1曲目「Heaven」は、2024年開催の草月プラザ・イサムノグチ石庭『天国』での公演『unpeople -初演-』で披露された Jatinder Singh Durhailay(ジャティンダー・シン・ドゥハレ)、Johanna Tagada Hoffbeck(ジョアンナ・タガダ・ホフベック)とその愛鳥Lemon(レモン)、大崎清夏による詩のポエトリー・リーディング作品。 2曲目「Pragma」はクラブセットでパフォーマンスをしているリズムトラック。3曲目は2023年にリリースされた「one window」のインストゥルメンタルバージョンで先行配信中の「one window (instrumental)」。そしてEPの最後を飾る4曲目は7分間の壮大な「Pluralist」。マスタリングはメトロポリス・スタジオのMatt Colton(マット・コルトン)が手がけている。
アルバム『unpeople』同様に田中せりがアート・ディレクションを担当し、池谷陸による写真がアートワークに起用されている。音楽的方向性、そしてビジュアルワークからも前作『unpeople』の残り香が漂うような、蓮沼執太による音響世界が作られている意欲的な小曲集となっている。ライターhiwattによるライナーノーツが届いた。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
『+1P EP』ーそれぞれの調和を直列で実現していくためにー
Text by hiwatt
90年代の半ばに生まれ、00年代にかけて電子音楽のシーンで流行したグリッチ・ミュージックだが、近年、再び賑わいを見せている。PCでの個人的な音楽制作が始まった時代に、偶発的(あるいは意図的)に生じた、ランダムな音飛びやノイズのような電子回路のエラーを、音楽に取り入れたものだ。そんなグリッチ・ミュージックが回顧されている今、当時の日本の俊英たちに再び脚光が当てられているが、蓮沼執太もまた改めて注目すべき音楽家だ。
彼の2006年のデビュー作『Shuta Hasunuma』は、アンビエント的な意味合いを含んだ環境音をバックに、アコースティックな演奏と、デジタルなグリッチノイズが絡み合う、“三元論的なアプローチ”が、今の耳で聴いても新鮮だ。それに加え、今日にも通ずる彼のポップセンスや、コンポーザーとしての巨大な才覚を垣間見ることができる。最近のグリッチ・ミュージックの定型の一つとして、環境音とグリッチという、アンコントローラブルな2つのマテリアルを組み合わせた作品が多いが、彼は弱冠23歳ながらにそれを試みていた。
ジャンルとしての、グリッチ・ミュージックの最後のピークポイントは、間違いなく2005年であったが、彼はそんな狭間の時代にも探求を続けていた。2007年には、アヴァンギャルドな『HOORAY』と、メロディアスな『OK Bamboo』という対極的な作品をリリースし、2009年の『POP OOGA』では自身の歌唱を取り入れたポップスに挑むなど、多軸的にグリッチの活路を探る。以降は、蓮沼執太フィルでの活動に加え、ソロ名義のコンピレーション作品では初期の作風を更新し続けた。他にもU-zhaanとの共演では、タブラという音階を持ったプリミティブな打楽器と、グリッチやクリック、アンビエントのようなデジタルサウンドをシームレスに演出し、前人未到の新境地を見せた。
エレクトロニカ主体のオリジナルアルバムとしては、15年ぶりに発表された『unpeople』は、“人間がいない”という、2010年代に経験した他者とのコラボレーションへの、反語的とも言えるタイトルを冠した作品。ただ、それはコロナ禍に制作されたバックグラウンドも大きく影響しており、データを送受信することで、地球の裏側のアーティストと簡単に音楽を共作できてしまうテクノロジーの進化や、加速度的に音楽界へと普及しているAI技術に対する、実存主義的な視点の問いかけとして、非常に深い意義がある。蓮沼の持ち味とも言えるメロディが後退し、気難しさや冷淡さすら感じるかもしれないが、種々雑多な音楽性のスケッチが、多岐にわたる人脈の音楽家たちと共に紡がれていく様を追っていくと、他者の存在を求め、引き立て合うことの美しさに触れることになる。
そんな『unpeople』を経て、2015年の『メロディーズ』のライブ以来、約10年ぶりに企画されたソロライブのパフォーマンスシリーズが《unpeople+1 people》だ。“空間の中に音を落とし込む”という強い意識を持って、会場ごとに変化を重ね、1 people、つまり1つの共同体(オーディエンス)に対して演奏することで練られたこのプロジェクトは、アウトプットと同時に、インプットされたものも大きかったのだろう。
そうして、新たなインプットから生まれたのが最新作『+1P EP』だ。この作品は、最も蓮沼らしいとも言える、ボタニカルなエレクトロニクスをバックに、Jatinder Singh DurhailayとJohanna Tagada Hoffbeck、そしてその愛鳥Lemonが、大崎清夏による詩を詠む「Heaven」から始まる。他者が介在するこの“愛おしさ”が、『unpeople』に対する回答であり、問いに対する問いかけにも思える。バックトラックのムードを保ちながら、グリッチビートが煌めく、フロアライクな「Pragma」に移行するが、極めて対人的な意図を持ったトラックだ。そこから展開される「one window」のインストゥルメンタル・バージョンによって、再び物理的な“無人”を感じることになり、無限の虚無空間のようなサウンドスケープを見せる「Pluralist」で、絶望とも希望とも言い難いエンディングを迎える。
蓮沼執太という音楽家は、多元論者(Pluralist)のようでもあると感じていたが、おそらく間違いではなかったようだ。初期の作品から、全くもって異なるマテリアルの音を調和させることに秀でていた。彼が鳴らすアンビエント、アコースティック、グリッチ/ノイズ、これらを何に喩えるかは聴き手次第であるが、これらを並列に鳴らして調和をもたらすということは、並大抵の所業ではない。ただ、最近のプロジェクトでは、直列でそれを実現することを目指しているように思える。誰かに聴かせるという経験を経て、それが実現したのではないだろうか。